Youtubeを見てるときにふと、「私はYoutubeが趣味です」と初対面の人に言うことが出来るだろうかと考えたときにできないなと考え、それはなぜかと疑問が湧いたので言語化したいと思います。
「趣味とはなにか」
本題です。私は考えた結果趣味を下記の様に定義しました。
- 「それ」はやってて楽しいこと
- 「それ」はやった後に罪悪感がないこと
- 「それ」は話題を広げられること
この3つを満たしたときに初めて趣味と言えるのではないかと考えました。一つずつ解説します。
「それ」はやってて楽しいこと
大前提ですね。僕は医学の勉強が嫌いだけど、楽しそうな人もいますね。(河野玄斗など)
「それ」はやった後に罪悪感がないこと
僕が冒頭の「Youtube趣味論」に疑問を持ったきっかけです。僕は怠け者なのでダラダラYoutubeを見ることが多々あるのですが、見た後にすごい罪悪感を感じてしまいます。僕がYoutubeを見た後罪悪感にさいなまれるのは「何にもつながらない」と思っているからでしょう。例えばyoutubeで見た動画を面白おかしく人に話す人はyoutubeを趣味だと言ってもいいでしょう。なぜなら、「youtubeを見ることで話題が増える」→「人に話す」→「話題を増やすためにyoutubeを見る」といったサイクルがあるからです。
積み上がるものがあれば罪悪感なんて起こらないですからね。
「それ」は話題を広げられること
衣食住や生理現象は趣味に入るのかを考えた結果、趣味を定義する項目として作りました。
僕は服は着ないより着たほうが楽しいですが、服に関して語ることはあんまりないです。一方でアパレル業界に務める人もいますよね?
僕は食べるの好きだし、それなりに語ることもできますが、世の中には何十年同じメニューで生活する人もいるかも知れません。
趣味は最低限人に語れるだけの核を自分の中で形成しないと行けないということです。同じように何も考えずに動画鑑賞、読書をしていても趣味と言えませんね。
以上が僕の趣味論です。
※3/4更新
趣味論のアップグレードをします。以下一部趣味論の再定義と趣味でないユーチューブの危険性について解説します。
再定義:趣味とは何かを生み出すものである。
- 「それ」はやった後に罪悪感がないこと
- 「それ」は話題を広げられること
以上二つの定義を「趣味とは何かを生み出すものである。」に集約しました。
理由は、「それ」はやった後に罪悪感がないことの解説が「なにかを生み出す」というテーマでまとめたほうがしっくり来たことと「それ」は話題を広げられることを「話題を生み出す」と言い換えてもいいと思ったからです。
以上と第一の定義「それ」はやってて楽しいことをあわせて一つの定義にすると
「趣味とは楽しく何かを生み出すものである」
となります。
趣味でないユーチューブ鑑賞の危険性
つまり、ダラダラ目的無くユーチューブを見てしまうことへの危険性について解説します。朝起きて布団でゴロゴロ、寝る前に布団でゴロゴロ気がつけば1,2時間経っていた経験。皆ありますよね?その経験が危険なんです!
『スマホ脳』によればアウトプットしない情報を大量に詰め込むことで認知症に似た症状になることが知られていて、これを「スマホ認知症」と定義しています。
ユーチューブだけでなくツイッターやアニメや漫画でも同様です。だめなのは考えずにコンテンツを享受してしまうことです。完成度が高い(考える余地のない)コンテンツ目的なく見続けることで脳は考えることをやめてしまうのです。特にユーチューブをやり玉に上げる理由がこれです。動画というコンテンツは人の五感のうち目、耳を支配し、思考のきっかけとなる感情(喜怒哀楽)を奪ってしまいます。
お笑いをみて笑ってるときに何も考えてない例や動物の動画をもてほっこりするとき何も考えていない例などがこれに当てはまりますね。
ユーチューブの特性に視聴者が好きそうな動画を関連に出す機能があります。この機能によりさっきみていた動画がなぜ面白かったかを理解する間もなく次から次へと動画を見続けてしまうのです。
動画という完成度の高いコンテンツと考える間を与えない関連動画機能が前述した「スマホ認知症」条件を満たすことは明らかです。ユーチューブは「スマホ認知症」を作り出すのに最適な媒体なのです。そして、意味もなくユーチューブを見る人間の脳は歴史上類を見ない速度で破壊されているのです。
解決法としてユーチューブの代わりに本を読むことがおすすめです。本は完成度の低いコンテンツであり、本を読むときに人の脳は無意識に本の内容を色々な角度から考えるためです。
能動的なアウトプットも効果的です。ユーチューブを見たら人に内容を話す、ノートに書き起こすなどでできる限りアウトプットを図りましょう!

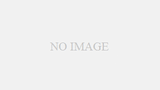
コメント